数多く詠まれた万葉の歌。その中でもここ妹山・背山を歌枕として詠んだ句は15首にものぼります。寄り添うようにやさしい山姿に、都に残してきた愛しい人への想いがふくらんだのせしょうか。
ここにご紹介する歌や解釈は和歌山県が発行した「紀伊万葉ガイドブック」、監修 村瀬憲夫(近畿大学文芸学部教授)を引用させていただいております。
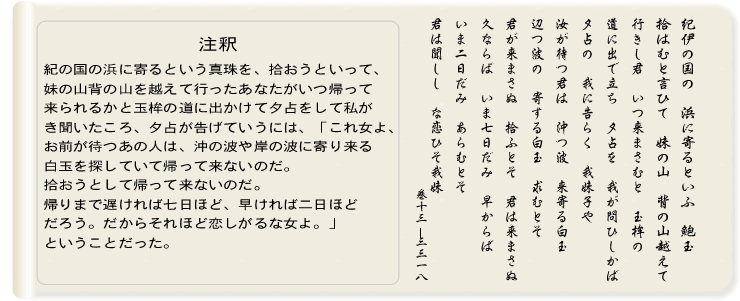
これやこの 大和にしては 我が恋ふる 紀路にありといふ 名に負ふ背の山 ( 巻1-35 阿閉皇女)
(これやこの やまとにしては あがこふる きぢにありといふ なにおふせのやま)
 紀州路にあるとしてかねて大和で私が心ひかれていた背の山。これこそまさしくその名にそむかぬ背の山よ。
紀州路にあるとしてかねて大和で私が心ひかれていた背の山。これこそまさしくその名にそむかぬ背の山よ。
【句碑は背ノ山にあります。】
真木の葉の しなふ勢能山 しのはずて 我が越え行けば 木の葉知りけむ (巻3-291小田事)
(まきのはの しなふせのやま しのはずて わがこえゆけば このはしりけむ)
真木の葉がよく茂りたわむ背の山を、私はゆっくり賛美することもできずに越えてゆくが、木の葉は私のこの気持ちを分かってくれたであろう。
妹に恋ひ 我が越え行けば 背の山の 妹に恋ひずて あるがともしさ ( 巻7-1208)
(いもにこひ あがこえゆけば せのやまの いもにこひずて あるがともしさ)
 妻への恋心に苦しみつつ山路を越えて行くと、背の山が妹の山と一緒にいて恋い苦しんでいないのが羨ましいことよ。
妻への恋心に苦しみつつ山路を越えて行くと、背の山が妹の山と一緒にいて恋い苦しんでいないのが羨ましいことよ。
【句碑は道の駅「紀ノ川万葉の里」にあります。】
たくひれの かけまく欲しき 妹の名を この勢能山に かけばいかにあらむ (巻3-285 丹比真人笠麿)
(たくひれの かけまくほしき いものなを このせのやまに かけばいかにあらむ)
口に出して呼びたい「妹」の名を、この背という名の山にかけて口にしてはどうだろう(背の山に代えて妹山といったらどうだろう)
宜しなへ 我が背の君が 負ひ来にし この背の山を 妹とは呼ばじ (巻3-286 春日蔵首老)
(よろしなへ わがせのきみが おひきにし このせのやまを いもとはよばじ)
結構なことにもわが背の君同様「背」という名を持つこの山を今さら妹山とは呼びますまい。
勢能山に 黄葉常敷く 神岡の 山の黄葉は 今日か散るらむ (巻9-1676)
(せのやまに もみちつねしく かみおかの やまのもみちは けふかちるらむ)
旅路の背の山に紅葉が絶えず散り続けている。大和の神岡の山の紅葉は今日散っているだろうか。
紀伊路にこそ 妹山ありといへ 玉くしげ 二上山も 我こそありけれ (巻7-1098)
(きぢにこそ いもやまありといへ たまくしげ ふたかみやまも いもこそありけれ)
紀の国に妹山があるというが、二上山だって妹山があったことだ。
妹があたり 今そ我が行く 目のみだに 我に見えこそ 言問はずとも (巻7-1211)
(いもがあたり いまそわがゆく めのみだに われにみえこそ こととはずとも)
妹山を通り、妹のあたりを今こそ私は通っているのだ。せめて幻の中にだけでもわが妹(妻)は見えてほしい。ことばはなくとも。
後れ居て 恋ひつつあらずは 紀伊の国の 妹背の山に あらましものを (巻4-544 笠朝臣金村)
(おくれゐて こひつつあらずは きのくにの いもせのやまに あらましものを)
後に残って恋い苦しんでいないで、あなたの歩いていく紀の国の妹背の山でありたいものを。
背の山に 直に向へる 妹の山 事許せやも 打橋渡す (巻7-1193)
(せのやまに ただにむかへる いものやま ことゆるせやも うちはしわたす)
背の山に真向かいの妹の山は、背の山のいう事をきいたのか、妹の山には打橋を渡していることよ。
麻衣 着ればなつかし 紀伊の国の 妹背の山に 麻蒔く我妹 (巻7-1195 藤原 卿)
(あさごろも きればなつかし きのくにの いもせのやまに あさまくわぎも)
麻の衣を着ると懐かしく思い出される。紀の国の妹背の山に麻をまくいとしい子よ。
人ならば 母が最愛子そ あさもよし 紀の川の辺の 妹と背の山 (巻7-1209)
(ひとならば ははがまなごそ あさもよし きのかはのへの いもとせのやま)
もし人間だったら母の最愛の子であろう。紀の川沿いの妹山と背の山よ。
我妹子に 我が恋ひ行けば ともしくも 並び居るかも 妹と背の山 (巻7-1210)
(わぎもこに あがこひゆけば ともしくも ならびをるかも いもとせのやま)
いとしい妻を恋いつつ旅を行くと、うらやましいことに並んでいるよ。妹の山と背の山は。
大汝 少御神の 作らしし 妹背の山を 見らくしよしも ( 巻7-1247 柿本人麻呂歌集)
(おほなむち すくなみかみの つくらしし いもせのやまを みらくしよしも)
大汝(大国主)と少御神(少彦名)に神々がお作りになった妹背の山は見るとりっぱなことよ。
