名草山 言にしありけり 我が恋ふる 千重の一重も 慰めなくに
巻7−1213
(なぐさやま ことにしありけり あがこふる ちへのひとへも なぐさめなくに)
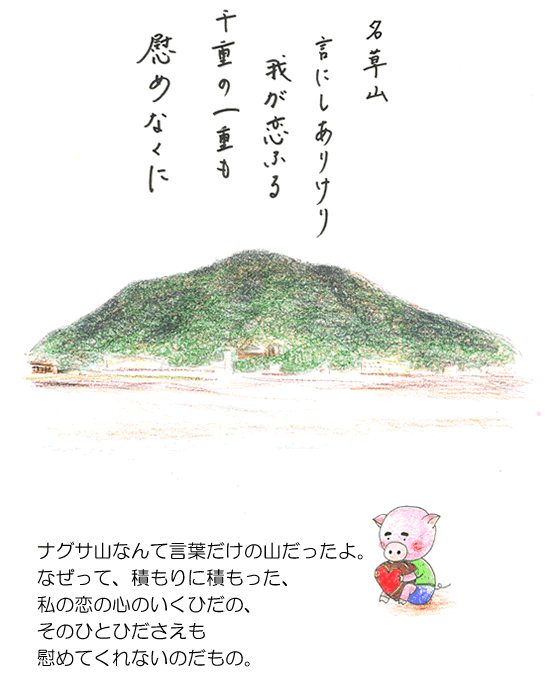
詳しい解説
この歌も神亀元年の紀伊国行幸の折に、お供の官人(役人)の一人が詠んだものと推定できます。名草山は和歌の浦になくてはならない山です。和歌の浦の東方に穏やかにゆったりと鎮まっています。下の写真をご覧ください。
名草郡(現和歌山市)を代表する山で、標高二二九メートルと低いですが、付近から独立していますので、目につく存在です。中腹には西国二番札所の紀三井寺があります。ちょうど飛鳥の三輪山に似て、まろやかにやさしい山容をしています。この山が、鏡のように波静かな和歌の浦の水面にゆったりと影を落としているさまは、本当に絶景です。あわただしい世相に生きる現代の私たちに、心の靜もりと安らぎをもたらしてくれる山であり光景です。
万葉びともそのように感じたようです。ただ歌の表現としては、名草山は言葉だけのものだったよと、作者の心は慰められなかったと歌われていますが、このやさしくおだやかな名草山のたたずまいに心ひかれ、旅愁が慰められたからこそ、このように明るく軽やかな調子で歌うことが出来たのでしょう。


